映画 ポー川のひかり Review
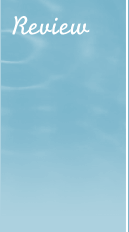
- 2009.6.20 Figaro japon
ひとと交わり美しいものを見る、というすぐそばにある贅沢さ。
小沼純一(音楽批評家・詩人) -
衝撃的な冒頭シーン、もはやミステリーしたてかとはやる気持ちを抱きつつ、展開は意外な方向にむかう。そして映画の後、ぼんやりと街を歩きながらふと想いだしたのは清貧という言葉だ。
清貧、いつから耳にしなくなったろう。バブル期が終わる頃に流行したのは一種のアンチテーゼでもあったか。つづく景気の低迷のなかではわざわざそんなことを言う意味もないまま、現在に至っているようにも思えなくもない。主人公の若き大学教授、哲学の研究者は、大学を捨て、郊外にむかう。手にしているものを次々に捨ててゆく。生活をする最低限のものだけが残り、そのまま誰のものでもない土地で、さぶれた家を修復して暮らし始める。
世捨て人、理想論者、形容はいくらでもできよう。わたしたちはすでに、歴史のなかに、こうした生き方をする人を何人も知っている。東西の宗教家のイメージを重ねるのも難しくない。ならば、ありきたりで使い古されたもの、時代錯誤にすぎないと一蹴できるだろうか。そうするにしては、元・大学教授が川のほとりで目にするものの何という豊かさか。降ってくる雨、草に落ちる雫、虫、花。はねる魚。ながれる雲。瞬間の光。ひとつひとつのシーンに、古代の哲人が宇宙を成り立たせていると考えた五大元素―火が、地が、風が、空が、水が、ある。そうしたなかにあって、元教授のそばを通り過ぎ、また訪れてくる、一日一日を十全におくる人たち。大学での学問、本や文学を媒介にして伝えるのではなく、身近にひとと声を交わし、手に触れるものにこそむかってゆくこと。たしかにキリスト教の、聖書の教えの反映がしばしばある。だが、この感覚的なよろこびは、聖書をイタリアという気候風土で翻訳し、映像化してこそ成り立つものだ。
『ポー川のひかり』は、生きてひとと交わること、美しいものを見ることの、清貧のなかに秘められた、わたしたちのすぐそばにある贅沢さを照らしだす。
- 2009.6.20 てんとう虫
書物ひとすじの世界から日常の営みに目覚めた
キリストさんと呼ばれた青年の物語
青山南 -
『ポー川のひかり』とはなんとも叙情的なタイトルだが、これは邦題で、原題まるで味わいはちがって、「百本の釘」。映画のほぼ冒頭にあらわれる、じつに衝撃的なシーンに由来する。
イタリアはボローニャ大学の古文書をおさめた部屋。夏休みがはじまった日、その事件は発覚した。とりみだした守衛の通報に、警察は、殺人か、と駆けつけるが、惨状には絶句、「まさに大虐殺だ」とつぶやく。おそろしくぶっとい釘が、百冊の古文書にぐさりと刺さっていたのだ。
本は言うまでもなく、生き物ではない。しかし、誰かが遺していった言葉でできているのだから命の残照はあり、読ませることによってそれがよみがえることもあるのだから、ある意味、生きている。そんな本のあやうい命が完全に絶たれたかのような印象を与える、圧倒的な迫力のシーンだ。書物を素材にした凄まじいアートであるとも言ってもかまわない。これだけでも必見だ。書物への熱愛なしでは、こんな完璧な虐殺はできなかった。犯人捜しの映画でないので犯人はすぐにわかるのだが、書物を信頼して書物をよすがに生きてきた若い哲学教授の犯行。書物は世界に混乱を招いただけではないのかという苛立ちが動機である。
なんとピュアな、笑ってはいけない。うつくしいポー川のほとりに身を隠して、貧しきひとたちと交流する日々に驚きと平安を見出し、目を鮮やかにかがやかせる青年の姿は神々しいほどなのだから。じっさい、村人はかれをキリストさん、と呼ぶ。